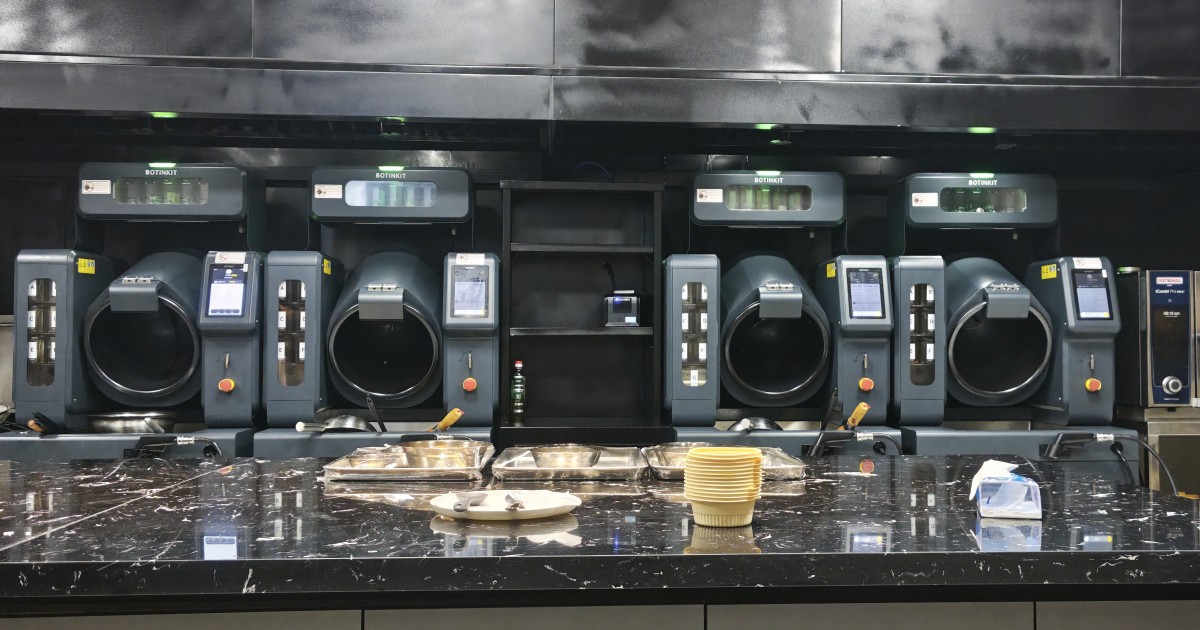ロボットが走る、跳ぶ、舞う!中国が仕掛ける壮大な「人材育成」の舞台裏
皆さん、おはようございます。中国深セン在住の吉川です。最近は深センも徐々に暑さが和らぎ、過ごしやすい日が増えてきました。街を歩いていると、コーヒーショップの店先でロボットが注文を取ったり、配送ロボットがせっせと荷物を運んでいたりする光景を日常的に見かけるようになり、改めて中国のテクノロジーの進化を肌で感じています。さて、今回はそんなロボット技術の中でも、特に注目すべき一大イベントについてお話ししたいと思います。
先日、北京の国家速滑館(ナショナル・スピードスケート・オーバル)で、世界初となる「世界ヒューマノイドロボット運動会」が開催されました。このニュースを聞いて、「え?ロボットの運動会?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。私も最初は少しコミカルな響きに感じましたが、その中身を知るにつれて、これは単なるエンターテインメントではなく、中国が国家戦略として仕掛ける壮大な「陽謀」なのではないかと確信しました。
「陽謀」の始まりは一本の「マラソン」から
今回の世界運動会に先立って、今年の4月には北京で「ヒューマノイドロボットハーフマラソン」が開催されました。このマラソン大会は、日本のメディアでも取り上げられ、転んだり、立ち止まったりするロボットたちのユーモラスな映像が大きな話題となりました。しかし、その裏側では、北京人形ロボットイノベーションセンターが開発した「天工」というロボットが、見事に完走し、世界初の記録を打ち立てたのです。
このマラソン大会は、一見すると「面白い実験」のように見えますが、実は技術的な挑戦が凝縮されていました。長距離を走り続けるためには、バッテリーマネジメント、熱制御、そして何よりも安定した歩行アルゴリズムが不可欠です。転んでもすぐに起き上がり、走り続けられる能力は、まさに過酷な環境での実用化を見据えた技術の集大成と言えるでしょう。
このマラソン大会が成功を収めたわずか数か月後に、より規模が大きく、競技種目も多岐にわたる「世界ヒューマノイドロボット運動会」が開催されたことは、決して偶然ではありません。これは、マラソンで成功した技術をさらに応用し、より複雑な動作や環境でのパフォーマンスを競い合うための、次なるステップだったのです。
「AI」による自律走行が勝利を分けた100メートル走