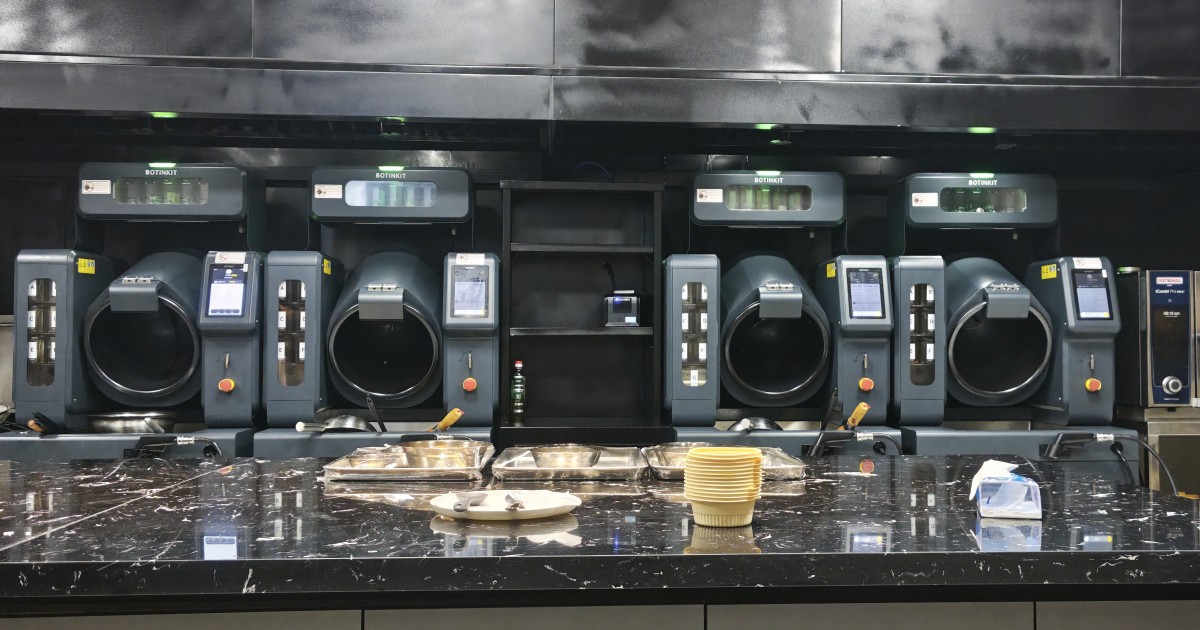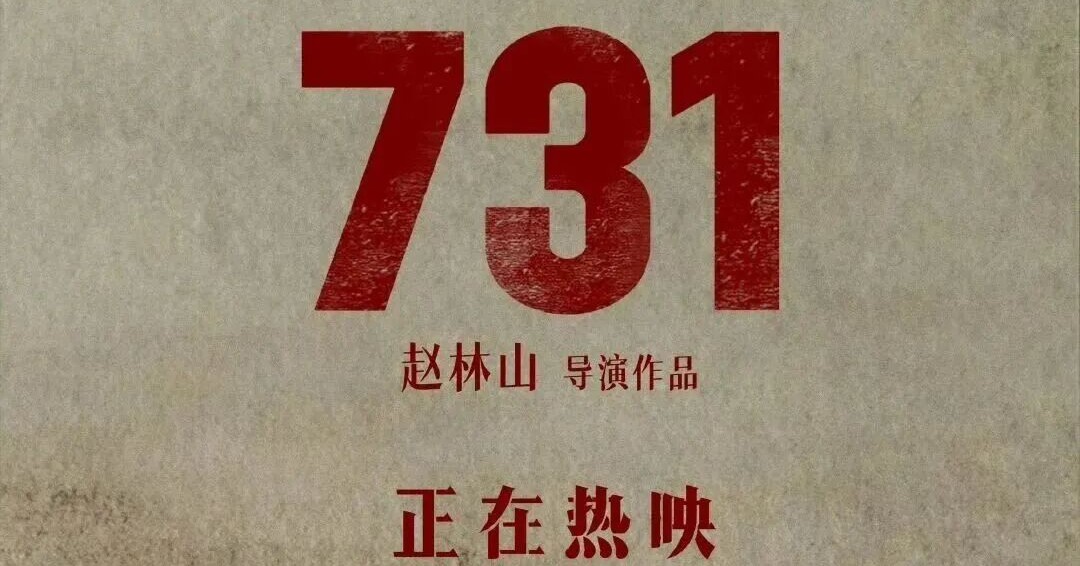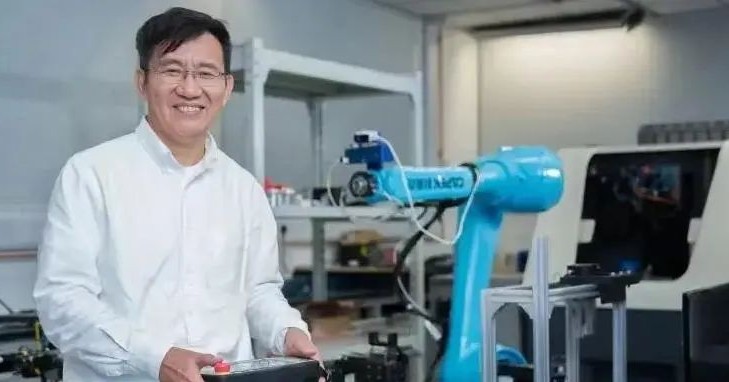「女性版安倍」新首相が日中ビジネスを強制リブート!サナエノミクスと円安加速、中国の「歴史カード」再燃の危機
皆さんおはようございます。中国深セン在住の吉川です。
先週、中国の国慶節(建国記念日)の大型連休の最中、日本の自民党総裁選の結果が飛び込んできました。高市早苗氏の当選というニュースに、思わず個人アカウントで半ば反射的に「日中関係悪化する」とツイートしてしまいました。

もちろん、中国の報道や日本の主要メディアの論調を追っていると、「極右」「強硬派」といったラベルが強力に貼られており、反射的にそう反応してしまったのですが、連休中にふと立ち止まって考えたのです。もしかしたら、私自身がメディアが作り上げた「高市早苗像」に洗脳されていただけではないか?
そこで、今回は高市氏について改めてリサーチをしました。特に、中国の現地メディアや識者が、この「女版安倍」とも呼ばれる新首相の誕生をどう受け止め、分析しているのか。そして、その政策が、我々が直面する日中ビジネスの現場にどのような現実的な影響をもたらすのかを、徹底的に掘り下げていきたいと思います。
「高市氏が首相になれば、対中関係はさらに冷え込むのか?」「我々のビジネスはどうなる?」—この問いに、多角的な視点から答えを出すことが、今日のニュースレターの目的です。
中国が注視する「女版安倍」の誕生:底色を変えぬ強硬路線
まず、高市氏の首相就任に対する中国側の第一報は、その右翼政客としての側面を極めて強く強調するものでした。中国の主要メディアは、彼女を「安倍晋三氏の絶対的な信奉者・追随者」、「安倍ガール」、「保守派の星」と呼び、その政治的バックボーンと路線継承を最重要視しています。
中国側が特に警戒心を強めているのは、その極めて強硬な対中姿勢です。
-
政治綱領:「修憲、拡軍、デカップリング」を明確に掲げている点。これは、中国から見れば、戦後日本の平和主義を根底から変え、対立軸を明確にする意思表明に他なりません。
-
安全保障:台湾海峡問題への積極的な関与、平和憲法改正、防衛力強化への意欲。特に、台湾を「日本にとって極めて重要な友人」と呼び、非公式な関係深化を公言していることは、中国の最も敏感な「核心的利益」に触れるものです。
-
歴史認識:靖国神社参拝や南京大虐殺否定など、極めて保守的な歴史観。これは、後述しますが、日中関係の安定にとって最大の不安定要素と見られています。
高市氏の当選は、単なる政権交代ではなく、「日本の社会政治が極右翼化していることの現れ」と、中国側は非常にセンシティブに捉えています。これは、従来の「政権の安定」や「親中・反中のバランス」といった観点から一線を画すものであり、日中関係の「新常態」を予感させるものです。
しかし、同時に中国の識者たちは、「政客はパフォーマンス芸術家である」という冷静な見方も示しています。野党時代と首相就任後では、外交という高次元の視点から政策が調整される可能性も否定していません。しかしながら、高市氏の「日本本土の利益を最優先する保守主義」という本音は変わらないだろうという見方が大勢を占めています。つまり、表向きは「戦略的互恵関係」の維持を謳いつつも、本質的な部分では一切譲歩しないという、非常にタフな交渉相手になることを予期しているのです。
サナエノミクスの核心:日中貿易を揺るがす円安と経済安保
高市氏が経済面で最大の旗印としているのは、言うまでもなくアベノミクスの継承、すなわち「サナエノミクス」です。この経済政策の方向性が、今後の日中間の経済関係に直接的かつ広範な影響を及ぼします。
1. 継続する金融緩和と「円安の常態化」
中国の金融分析機関(中金投行など)のレポートでは、高市氏がアベノミクスの「三本の矢」のうち、「金融緩和」と「財政拡張」の嗜好を強く持つと指摘しています。
-
日銀の利上げ:高市氏の保守的なスタンスから、当面は期待薄と見られています。彼女自身も「円安は輸出産業にチャンスをもたらす」と公言しており、長期的な円安基調は維持されるとの見方が有力です。政局の安定による一時的な円高はあるかもしれませんが、トレンドは変わりません。
この円安の常態化は、我々日本のビジネスマンにとって、以下のような深刻な二面性をもたらします。
-
メリット:日本の輸出産業や、観光立国を目指すインバウンド分野にとっては、競争力が格段に向上する追い風です。メイド・イン・ジャパンの製品は、円建てで見れば安価になり、中国を含む海外市場で売れやすくなります。
-
デメリット:一方で、日本で事業を行う企業や一般消費者にとって、中国産の輸入製品は相対的に割高になることを意味します。中国の「价廉物美(安くて良い品)」に依存してきた日本の市場にとっては、物価高騰の一因となり得ます。結果として、実質賃金はさらに下がり、生活の圧迫感は増すでしょう。
2. 「経済安全保障」を名目とした投資と外国資本の制限
高市氏の経済政策のもう一つの柱は、経済安全保障を名目とした政府支出の拡大です。彼女の政策は、以下のように日本の産業構造と外資規制に大きな影響を与えます。
-
「Japan First」の産業自主性:高市氏はサプライチェーンの再編と日本ファーストを掲げた産業の自主性を強く推し進めるでしょう。特に、半導体やAI、重要鉱物などのキー産業に対して、国家主導型の「政策的投入」を強化し、中国依存からの脱却を目指します。これは、日本の特定の先端技術分野の再興を促す可能性があります。
-
外国資本への警戒:中国の報道は、高市氏が外資や資本流入に対して「保守主義者」であり、より慎重な態度をとると分析しています。敏感な産業への外資審査の強化や、不動産投資や企業買収に対する資金源審査の厳格化が進むと予測。特に、中国資本が絡む投資や技術提携は、これまで以上に慎重なデューデリジェンスと、政府による審査を要することになるでしょう。
これは、中国企業の日本市場への投資や、日本で事業を立ち上げる際の「経営管理ビザ」の要件が、今後ますます厳しくなることを示唆しており、日本への進出を検討している中国企業にとっては、大きな障壁となり得ます。
越境ECとデジタル貿易の「合規化」加速:日中ビジネスの新ルール
高市新政権が、特に具体的な行動に出やすいと目されているのが、日中間における越境EC(Eコマース)やデジタル貿易の規制強化です。これは、高市氏の掲げる「日本本土の利益保護」という保守的基調に完全に合致するため、早期の政策実施が予測されます。
1. 「小包免税政策」の撤廃と税制の適正化
中国の越境EC業界関係者は、「2026年の小包免税政策(少額輸入品に対する関税・消費税免除)の撤廃」が、高市政権下で一気に現実味を帯びると予測しています。
-
政策の論理:この撤廃は、欧米の主要国との足並みを揃えつつ、日本国内のEC業者、すなわち本土の売り手の利益を保護するという点で、高市氏の保守的な主張と完全に一致します。
-
影響:SHEINやTemu、AliExpressなど、中国のプラットフォームを利用した日本の消費者への小口販売のコストが上昇し、中国セラーの競争力が一部低下する可能性があります。
さらに、海外企業が日本のECプラットフォーム(例:楽天市場、Amazon Japan)で販売する際の税務合規化も加速すると見られています。具体的には、プラットフォーム運営者に「代扣代繳(源泉徴収・代理納税)」を義務付ける制度の導入が、早期に実現するかもしれません。これは、中国のプラットフォームを利用する日本の消費者に対しても、今まで以上に正確な税務情報が求められるようになることを意味します。
2. ローカライゼーションとコンプライアンスが生き残りの鍵に
中国の越境EC業者へのメッセージとして、高市氏の就任は「日本の保守主義が急速に台頭している」ことの表れであり、日本市場で長くビジネスを続けるためには、以下の対応が不可欠であると結論付けられています。
-
ローカライゼーション:単なる輸出入ではなく、日本国内での法人設立、在庫管理、カスタマーサポートの体制強化など、「日本企業」に近い形での事業展開が求められます。単に商品を流すだけでなく、日本経済に貢献する姿勢が問われるでしょう。
-
コンプライアンス:税務、知的財産権、品質管理など、日本の法律・規制に対する厳格な順守が生命線となります。グレーゾーンでのビジネスは今後、極めて困難になるでしょう。
吉川の個人的観点:日中関係に投じられる「歴史修正主義」という劇薬
高市氏の掲げる政策は、一見すると「強い日本」を取り戻すための道筋に見えますが、深センから日中の現場を見つめる私には、いくつかの根本的な矛盾があるように感じられます。