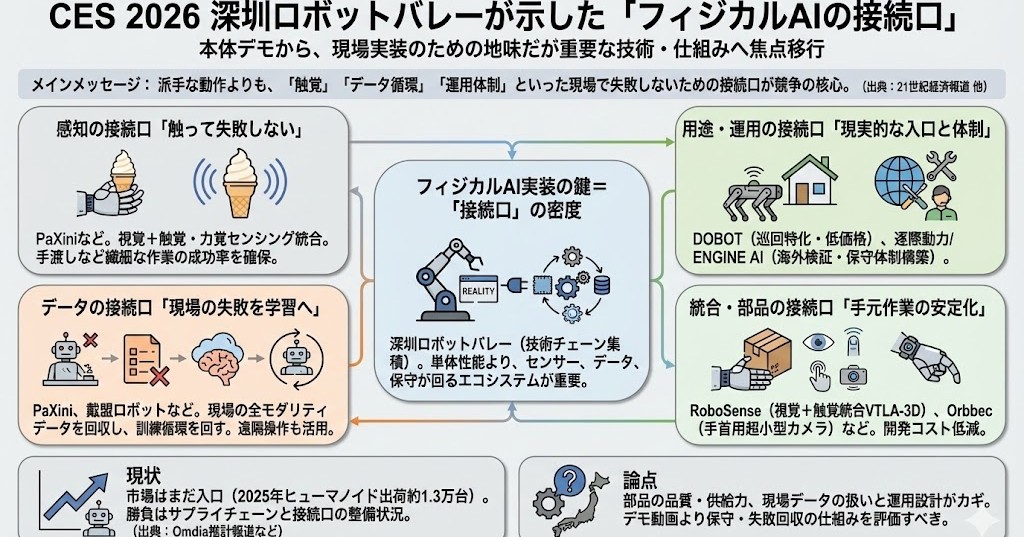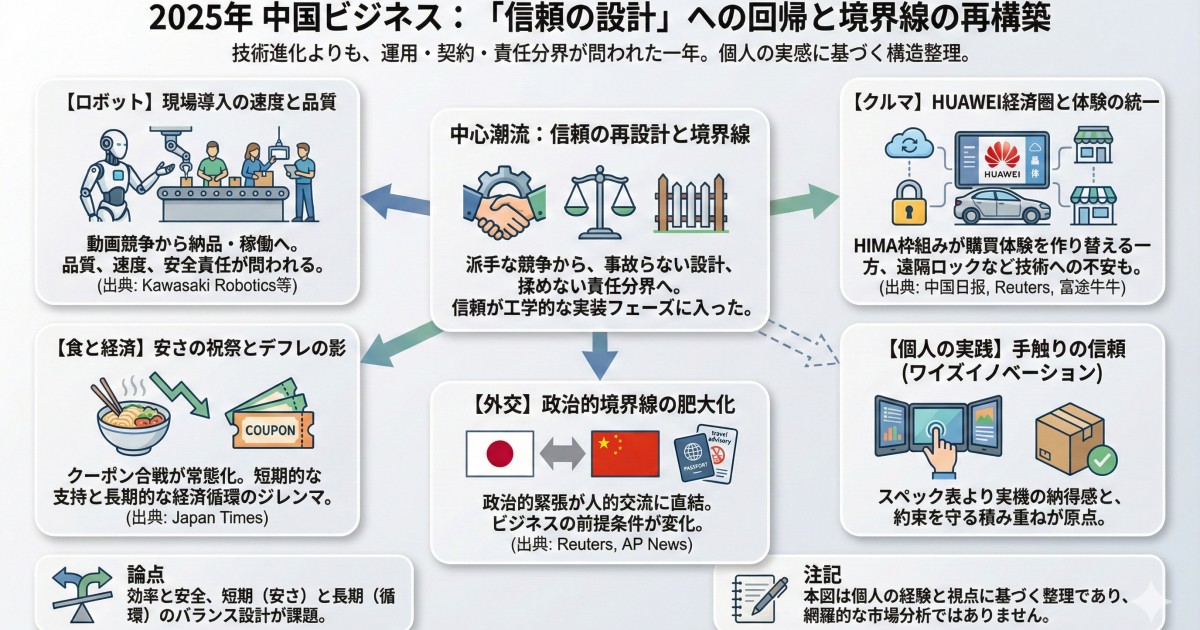くら寿司の中国撤退から読み解く日本外食チェーンの海外展開戦略と中国市場の現実
おはようございます。中国・深セン在住の吉川です。
日本国内で展開している自社ガジェットブランド「WiseeLAB」の事業が徐々に軌道に乗ってきました。先日、自社ECサイトに加えてAmazonでの販売もスタートし、Amazonユーザーの方にも気軽に手に取っていただけるようになりました。Apple Watchとスマホを同時に充電できるType-Cケーブルや3in1ワイヤレス充電器、耐久性の高い充電ケーブルなど、「こういうのが欲しかった」と思ってもらえるような実用性重視のアイテムを揃えています。
ご興味のある方はぜひ覗いてみてください。
さて本題ですが、今回は中国外食市場における日本企業の挑戦と撤退、そしてその中でも特に注目された「くら寿司」の中国事業撤退について、戦略的な観点から詳しく掘り下げてみたいと思います。競合他社であるスシローやはま寿司との比較を通じて、現地適応のあり方や価格設定の妙、SNS戦略の差異など、日本企業が今後中国市場で成功するためのヒントを読み解いていきます。
回転寿司チェーン大手のくら寿司が、2025年6月30日をもって中国大陸市場から完全撤退することを発表。2023年6月に上海で華々しく開業した1号店を皮切りに、10年間で100店舗展開という壮大な計画を掲げていた同社でしたが、わずか2年で約8190万人民元(約16億4000万円)の累積損失を計上し、事業継続を断念する事態となりました。
この撤退劇は、単なる一企業の失敗を超えて、中国市場における日本外食チェーンの戦略のあり方、そして急速に変化する中国消費者の嗜好について重要な示唆を与えています。なぜくら寿司は失敗し、競合他社のスシローやはま寿司は成功を収めているのか。その背景を詳しく分析することで、中国市場への参入を検討する日本企業にとって貴重な教訓を得ることができるでしょう。
また、この撤退の背景については、NNAが東京電力福島第1原発処理水の海洋放出を受けた中国の日本産水産物の輸入停止やトランプ米政権の関税措置などの逆風もあり、売り上げが計画通りに進まなかったというと報じましたが、これらの外的要因を撤退の主因とする見方については、客観的な分析が必要です。実際、同じ環境下でスシローをはじめとする競合他社は成功を収めていることから、より根本的な経営戦略上の問題があったと考えられます。

【中国】くら寿司、中国の全店舗閉店へ=年内めど(NNA)
news.yahoo.co.jp/articles/207b4… 【中国】くら寿司、中国の全店舗閉店へ=年内めど(NNA) - Yahoo!ニュース 大手回転ずしチェーンのくら寿司は、中国本土で展開する全店舗を年内をめどに閉店する。2023年の進出当時は中国で将来的に news.yahoo.co.jp
くら寿司の中国進出から撤退までの軌跡
くら寿司は日本では回転寿司業界第2位の地位を占める大手チェーンで、全世界で689店舗を展開する実力企業。同社は長年にわたり日本国内で「安全・安心・美味しい」をコンセプトとした回転寿司を提供し、特に添加物を使用しない「無添くら寿司」として消費者から高い評価を得てきました。
2023年6月、くら寿司は上海龙之梦城市生活中心に満を持して中国大陸1号店をオープン。このオープンは現地メディアも注目し、開業初日から長蛇の列ができるほどの盛況ぶりでした。店舗は日本の店舗を完全に再現し、看板メニューである回転寿司に加え、5皿集めると1回遊べる扭蛋機(ガチャポン)システムも導入しました。このエンターテインメント性の高いサービスは、当初SNSでも大きな話題となり、中国の若い消費者層の関心を集めました。

同社の中国進出に対する意気込みは相当なものでした。田中邦彦社長は当時、「10年以内に中国大陸で100店舗を展開する」という野心的な計画を発表し、中国市場への本格参入を宣言しました。この計画は、中国の巨大な消費市場と回転寿司への潜在的需要を見込んだものでしたが、現実は予想以上に厳しいものとなりました。
くら寿司は上海で3店舗(龙之梦店、美罗城店、金桥店)を展開しましたが、それ以降の出店は一切行われませんでした。当初の計画では、1号店の成功を受けて順次展開地域を拡大し、北京、深圳、広州などの主要都市への進出を予定していましたが、想定していた集客と収益を確保できず、拡張計画は早期に頓挫してしまいました。
財務面での深刻な状況
親会社である亜洲蔵寿司の財務報告によると、中国事業の赤字は年々拡大していました。2023年には2917万人民元(約5.8億円)、2024年には3783万人民元(約7.5億円)、2025年第1四半期には1490万人民元(約3億円)の赤字を計上し、累計損失は8190万人民元(約16億400万円)に達しました。これは1日当たり約11万人民元(約22万円)の赤字に相当する深刻な状況でした。
この数字の背景には、中国市場特有の高い店舗運営コストがあります。上海の一等地に位置する龙之梦店の賃料は月額数十万人民元に上り、加えて人件費、食材調達費、設備維持費などを含めると、相当な固定費が発生していました。一方で、想定していた売上高を確保できず、単月黒字の達成すら困難な状況が続いていました。
さらに問題となったのは、店舗当たりの平均客単価が当初の予想を大幅に下回ったことです。開業当初は1人当たり120人民元程度の消費を見込んでいましたが、実際には80人民元程度にとどまり、来店頻度も予想を下回りました。これは後述する商品品質や価格設定の問題とも密接に関連していました。
中国消費者が指摘する根本的な問題
この記事は無料で続きを読めます
- 価格戦略の失敗と市場適応の困難
- 成功企業との戦略的な差異
- 商品戦略における根本的な違い
- 価格戦略と市場ポジショニングの巧妙さ
- 外部環境要因の影響と客観的分析の必要性
- 中国市場特有の消費者行動と文化的背景
- 日本企業が学ぶべき戦略的教訓
- 中国外食市場の今後の展望と機会
- くら寿司の再挑戦への期待
- プロフィール
すでに登録された方はこちら